公務員から民間企業へ転職を考えるとき、「民間企業に行くこと」に不安を感じませんか。
私も実際そうでした。
「公務員しか経験したことがない私が、今更民間で通用するのか?」「これまで数値で表せるような実績を残していないけど大丈夫か?」こんな不安をもっている人は多いと思います。
結論から言うと、公務員と民間企業のギャップの大きさは転職先によって大きく変わります。
大きく違う部分もあれば、大して変わらない部分もあります。
私は、22年間国家公務員として働き、47歳で民間企業に転職しました。
実際私が経験したことを皆さんにお伝えします。
この記事を読むことによって、公務員が考える民間企業のイメージとのギャップを埋めるのに役立ちます。

民間企業をよく知らないから不安になる

知らないことを想像しようとすると、自分の経験で考えようとする。
どれぐらい民間企業のことを知っていますか


私が公務員を続けるかやめるか考えているとき、公務員を退職したところで何で生計を立てるか?という大きい不安がありました。
考えられる選択肢は、「民間企業に就職する」か「自分で事業を起こす」
自分で事業を起こすイメージが沸かなかったので、民間企業に就職する選択しました。
一番の懸念は、「公務員しかやったことがない自分が民間で通用するのか」といった不安でした。
なぜ民間で通用するか不安になったのか?
原因は、私が民間企業のことをよく理解していなかったからです。
民間企業とはどんなところで、どのような働き方をしているのか?公務員から転職するか悩んでいたときの私には民間企業の情報が圧倒的に足りていませんでした。
公務員が抱きがちな民間企業のイメージ
私が持っていた民間企業へのイメージは次のとおりです。
- 景気に左右され給与・ボーナスの変動が大きい
- 営利企業であることから実績主義が一般的
- 公務員より柔軟な仕事ができる
- 福利厚生や、勤怠管理はよくわからん
公務員はお堅い職業だと言われます。
公務員とは違い仕事面で自由度が高い融通が効く反面、数値化した成果が求められるところ、私の民間企業に対するイメージはこうでした。
自分たちの思い込みが不安を大きくしていく
長年の公務員生活を通じて、型にはめられた仕事をやっていると、変化しなくて良い心地よさを感じるようになります。
この変化しなくて良いという心地よさが、自由度が高い民間企業でに馴染めるのかという不安につながっていきます。
安定した給与や年功序列も、民間企業とのギャップに感じるポイントの一つです。
先が見通せる公務員は、不確定要素が大きく、振れ幅が大きい民間企業で下振れしたときを想像することで、不安を増大させていきます。
民間企業って本当に自由?事前に押さえておきたい現実
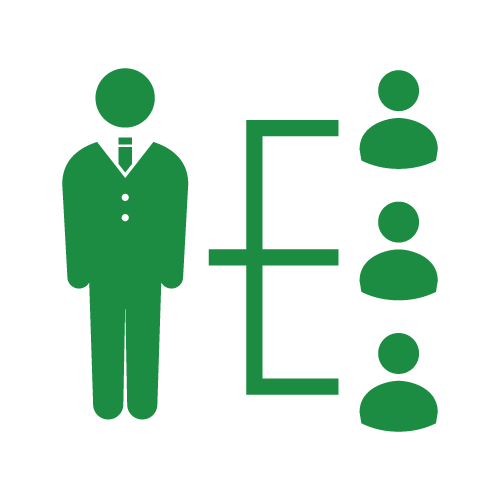
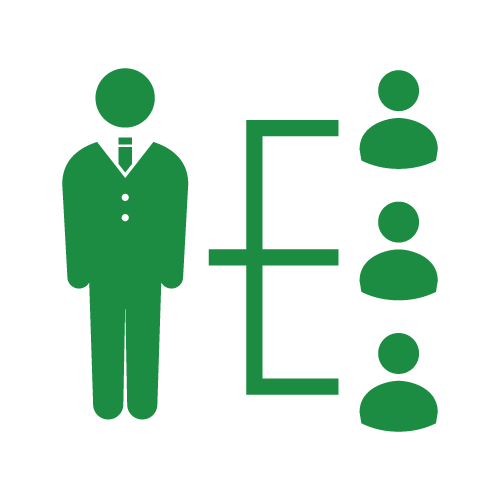



民間企業は公務員より自由度が高いと思いがち。
実態は、会社によって公務員のような会社もあれば、ゆるい会社もあるというのが現実です。
その企業がどんな風土を持っているのかは次のような条件に左右されます。
- 会社の成り立ち(歴史)
- 会社の担う使命
- 業界・業種
会社の成り立ち(歴史)による違い
歴史が長い会社ほど、自由度は低くなり公務員に近い会社が多くなります。
比較的若い会社はこれから成長していく過程にあるので、挑戦的な分自由度が高いです。
一方で長期安定している会社は、ルールやワークフローが確立されており、公務員に近いです。
会社の担う使命による違い
公共性の高い内容を仕事にしている会社ほど公務員に近い環境になります。
準公務員のような独立行政法人、電気・ガス・水道のような生活インフラ、医療・福祉事業などは法律上の制約が多く公務員に近い仕事環境です。
逆に、顧客の利便性向上や嗜好を満足させるような内容を仕事としている会社は自由度が高くなります。
業界・業種による違い
会社の担う使命とも関係しますが、小売業やIT関係などは自由度が高くなります。
一方で病院や福祉施設、官公庁を取引先とする大手企業などは公務員に近い働き方をする場合が増えます。
例えば私が経験した、外資系のゴルフショップなどは「印鑑禁止」であったり「不要な残業はせず早く帰る」ことが徹底されていました。
病院勤務時代は監督官庁への報告、検査や監査を受験したり厳格な仕事を求められます。現在は、官公庁を取引先とする電機メーカーに在籍していますが、公務員時代より古風な仕事の仕方をするような会社です。
民間企業と言っても、設立背景や使命、業種によって公務員のような働き方の職場もあります。
会社規模によっても傾向が分かれ、小規模な職場であれば意思疎通がしやすく自由度が高くなる一方で、大企業のような会社は硬直性が高く公務員のような感じになりやすい傾向です。
公務員から民間へ…一歩踏み出すための考え方





民間企業で働いている自分を想像できるか
民間企業の実態が見えないから、多くの公務員は不安を抱えモヤモヤしています。
そのためのヒントを2つ紹介します。
ヒント1 自分が求める変化を具体化する
どのような変化を求めているのか。
自分のもやもやを解決するためにどんな変化が必要なのか。
変化が小さすぎると物足りなく、大きすぎると負担になります。
ヒント2 第一歩が踏み出せる魔法の言葉
まだ、公務員から転職しようか迷っているあなたへ、魔法の言葉を教えます。
「自分はできる」と自分に言い聞かせることです。
闇雲に言っているわけではありません。
1964年に心理学者のロバート・ローゼンタールが提唱した「ピグマリオン効果」。
ローゼンタールが行った代表的な実験で、期待が意識的・無意識的な影響を与え、結果として期待通りの成果を生むというものです。
自分を心地よい環境に置くこと、自分を変化させることが可能であると信じることで次への一歩が踏み出せます。
ピグマリオン効果(ピグマリオンこうか、英語: pygmalion effect)とは、教育心理学における心理的行動の1つで、教師が期待をかけると、学習者の成績が向上する傾向が見られるという作用である。別名として、教師期待効果(きょうしきたいこうか)、ローゼンタール効果(ローゼンタールこうか)などとも呼ばれている。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
まとめ


公務員がなぜ転職に躊躇するのかについて解説しました。
多くの公務員は、民間企業がどんなところか分からないため、漠然とした不安に悩まされます。
- 給与の変動が大きい
- 実績主義
- 自由度が高い
- 福利厚生や、勤怠管理はよくわからない
よく分からないという民間企業に対する漠然としたイメージから来る不安が、転職に踏み出す足かせになっています。
実際に民間企業と言っても、公務員のような働き方をする会社から、ベンチャー企業のような自由な働き方をする会社までいろいろです。
- 会社の成り立ちや歴史
- 会社の担う使命
- 会社の業界や業種
歴史が長い会社、公共性の高い会社ほど公務員のような働き方をすることが多くなります。
一方でこれから成長していく会社、顧客の利便性や満足度を上げることを目的とする会社ほどより自由度が高くなります。
転職に踏み切るにあたって重要なのは、自分の望む変化が何かによります。
今、どんなモヤモヤがあるのか。モヤモヤをワクワク変えるには何をしたらいいのか。
仕事の変化が少なければ物足りず、大きすぎると負担に感じます。
自分にあったちょうどよい変化を見つけることが必要です。
「自分はできる」という魔法のことばがあります。
ロバート・ローゼンタールが提唱した「ピグマリオン効果」です。
民間企業を正確に分析できれば、転職への不安を解消したり小さくすることが可能取ります。
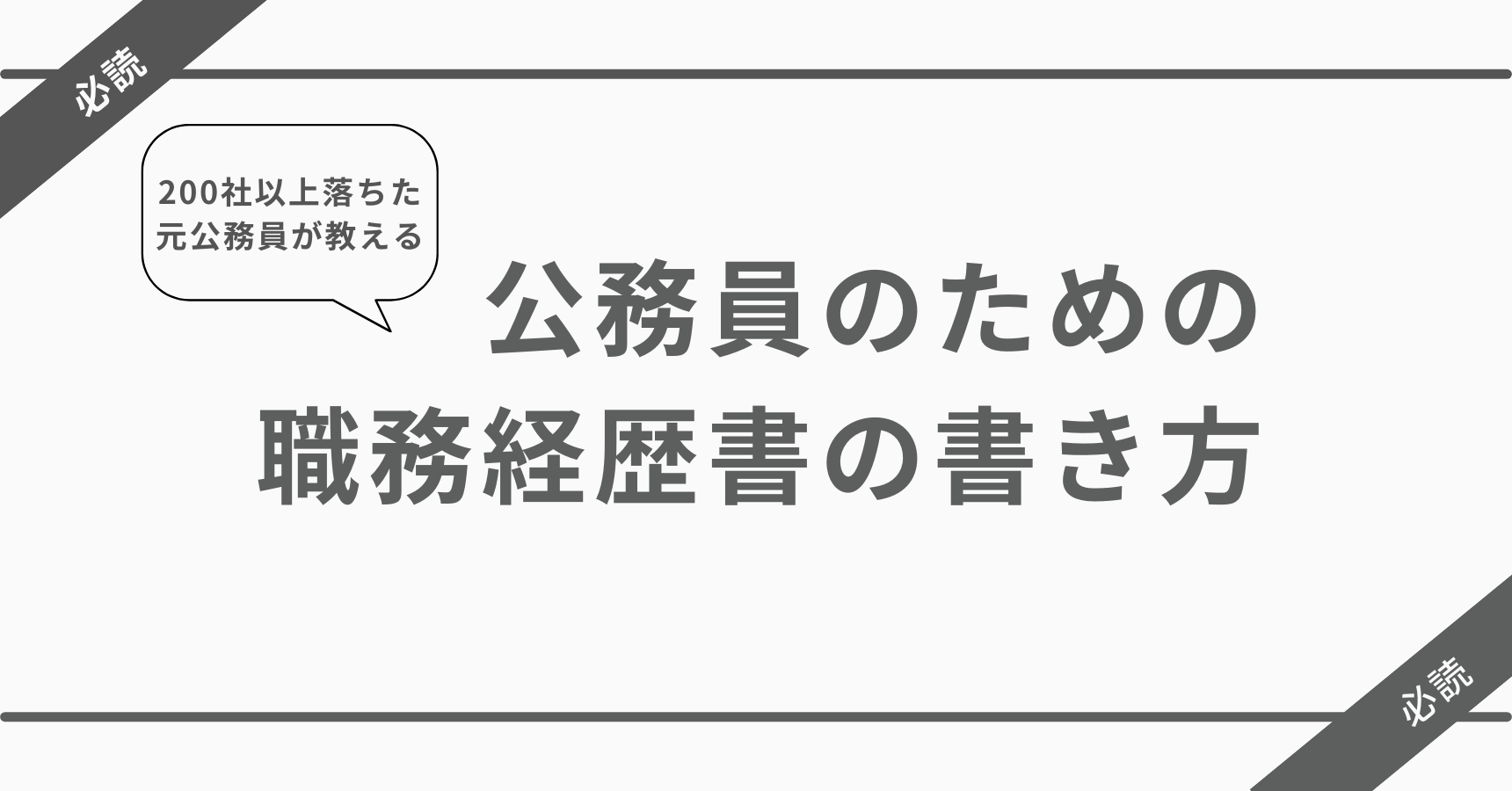
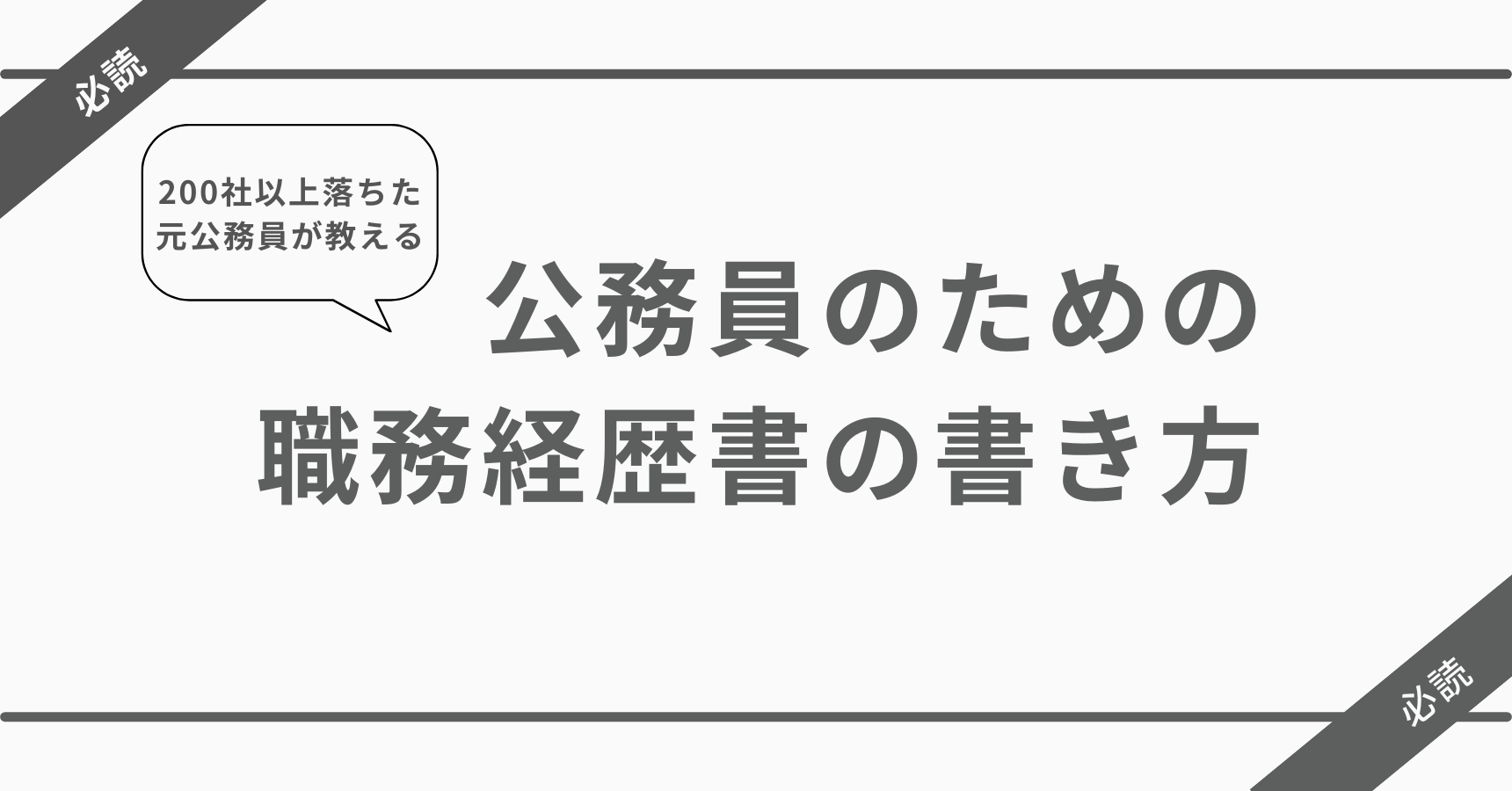
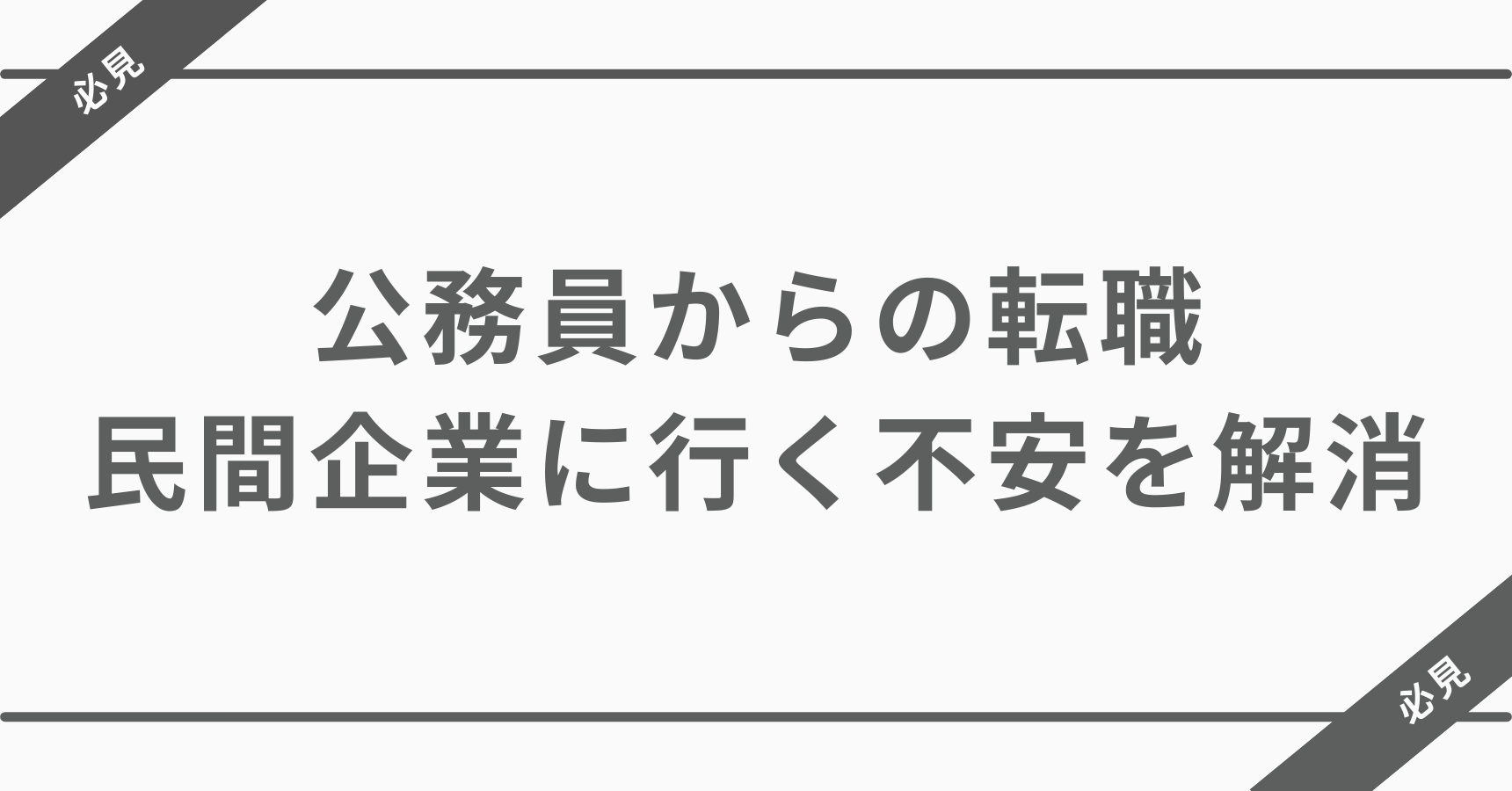
コメント